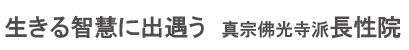真宗佛光寺派長性院の開山は、約700年前。
佛光寺中興の祖 了源上人の長息 空信が京都今熊野の地で開山。
以降、京の町や佛光寺と共に、その歴史を重ねてきました。
長性院の開基空信(性法)は、姓は源氏で、斎藤道獻(新田義貞の家臣)の孫と伝えられており、佛光寺第七代了源上人(中興上人・仏光寺教団の祖)の長息にあたる。正和二年(1313)山城国愛宕郡竹中庄(現・東山区今熊野日吉町新日吉神宮の地)に、法興寺を建立し、これを「西ノ坊」と称した。
当時の佛光寺教団は、親鸞上人の教えを広めるために、了源上人の御巡化と『交名帳』『絵系図』によって、多くの信者を獲得し、真宗における最大の勢力をもっており、当初、山科の興隆正法寺に於いて活動していたが、嘉暦二年(1327)後醍醐天皇から「阿弥陀佛光寺」の寺号を下賜され、三年後の元徳二年(1330)東山汁谷(現・東山区大和大路五条下る豊国神社の地)に移転し、佛光寺と称し隆盛を極めた。しかし、文明十四年(1482)佛光寺宗主・経豪は、当時の四十八坊中の四十二坊と数千の末寺・門徒を引き連れ、本願寺・蓮如に転じた。この時、西ノ坊第六世信乗は他の五坊と共に佛光寺に留まり、佛光寺第十四代経誉上人を助け、佛光寺の法灯を守った。
経過すること104年、天正14年(1586)、豊臣秀吉の懇請により佛光寺は、汁谷の地から、五条坊門高倉(現・下京区高倉仏光寺)に移転するが、これに伴い、西ノ坊第十一世大僧都「信秀」は、寺基を現在地に移した。 その後、寛永十年(1633)に寺号を「長性院」と改名し、現在に至っている。
天明八年(1788)、京の都を灰燼と化した所謂、天明の大火により、本山両堂と共に長性院も焼失するが、寛政元年(1789)に再建を果している。しかし、七十五年後の元冶元年七月(1864)、鳥羽伏見の戦いの兵火に罹り、再び本山共々長性院も全焼し、14年後の明治11年2月(1878)寺宇を完成した。しかし、同年五月、第二十一世信亮は、廃仏希釈等時勢激変の下で還俗したので、大善院住職良祐師が、長性院第二十二世住職を兼務した。
その後、明治39年三月(1906)自坊から出火、本堂、庫裏を失ったが、明治41年(1908)焼失を免れた座敷を、本堂兼庫裏に改築した。
昭和九年六月には、良祐の子息乾祐(乾三)が長性院第二十三世を継職し、昭和41年(1966)、老朽化が激しく且つ手狭な、本堂兼庫裏を新築し、改修を重ねて今日に至っている。
なお、度重なる火災のため、後世に伝えるべき資料・宝物を焼失したことは誠に遺憾である。唯一、長性院所蔵の『一流相承絵系図』は、嘉暦元年(1326)に描かれたもので、国の重要文化財の指定を受けているが、当院の絵系図には、俗人姿や女性、更には子供までもが描かれており、佛光寺教団の草創期における活動を伝える重要な資料となっている。
平成15年3月